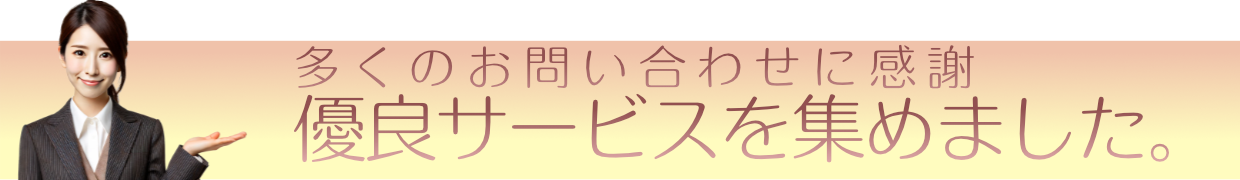更新日:2025年8月19日 | Miyo
2020年から学校で必修となったプログラミング授業は、特別な科目ではなく算数や理科などに組み込まれています。目的は難しい言語を覚えることではなく、物事を筋道立てて考える論理的思考を育てることにあります。
しかし、地域や学校ごとに取り組みの差があり、授業を受けた実感がない子も少なくありません。そのため家庭での学習が重要となり、本やアプリ、玩具などを活用することで理解を深められます。
自分の子どもが学んで成長する姿を見て、教育の遅れを補う家庭の力の大切さを実感しました。将来を担う子どもたちにとって、今の学びが未来を切り開く土台となるのです。

小学生のプログラミング授業はいつから?

小学校の授業にプログラミングが入ったのは最近のことです。 2020年度から全国で必修となり、すでに多くの子どもたちが学んでいます。
早い段階で取り入れられたのは、子どもの未来にとって欠かせない力になると考えられているからです。
必修化が始まった時期について
プログラミング教育は2020年から必修になり、子どもたちの授業に組み込まれています。
学年ごとの内容は学校ごとに異なり、算数や理科などの中で考え方を学ぶ形です。早くから学ぶことで論理的に考える力が強まり、未来を切り開く大きな力につながります。
- プログラミング教育は2020年から全国で必修になっています。
- 2019年から移行期間があり、段階的に授業が始まりました。
- 学年ごとの内容は決められておらず、学校ごとに工夫されています。
- 算数や理科の授業に考え方を組み込む形で学んでいます。
早い時期からの学びが、子どもの論理的思考を大きく育てます。
学校で学ぶプログラミングの内容とは
小学校のプログラミング教育は、特別な科目ではなく算数や理科、音楽などに組み込まれて行われています。
目的は言語を覚えることではなく、論理的思考力を育てることです。実際の授業では身近な教科の中で考える力を養う工夫が取り入れられています。
- 論理的思考力を育てることが大きな目的です。
- 算数や理科、音楽などに授業として組み込まれています。
- 新しい科目ができたのではなく、既存の授業の中で学びます。
- 難しいプログラミング言語を覚える必要はありません。
教科に組み込まれた学びで、子どもは自然に考える力を身につけます。
小学校で学ぶプログラミング教育の意味
プログラミング教育は「考える力」を育てるために行われています。 算数や理科などの授業に組み込まれ、正しい答えを出すことよりも、答えにたどり着くまでの考え方を大切にしています。
科目として独立しているわけではなく、教科の中で自然に学んでいくことが特徴です。
授業で目指していること
小学校でのプログラミング教育の目的は、言語を覚えることではなく、筋道を立てて考える力を育てることです。
さらに、コンピュータの働きや社会での役割を理解し、他の教科の学習を深めることにもつながります。身近な問題を解決しようとする前向きな姿勢も大切にしています。
- 算数などと合わせて学ぶことで理解を深める効果があります。
- プログラミング的思考を身につけることが中心です。
- コンピュータが社会で果たす大きな役割を理解します。
- 身近な問題を解決し、よりよい社会を考える態度を育てます。
目的は言語の習得ではなく、考える力と社会への理解を広げることです。
「プログラミング」という科目があるわけではない
小学校には「プログラミング」という専用の科目はありません。 国語や算数、理科などの授業に考え方を組み込み、正多角形を作る活動などで学びます。
パソコンを使うこともあれば、カードやゲームを使った学びもあります。小学校では基礎を養い、中学校以降で本格的に学んでいきます。
- 国語や算数、理科などに組み込む形で学びます。
- 専用の科目はなく、教科の中で自然に学びます。
- パソコンを使わないカードやゲームによる活動もあります。
- 中学校以降で本格的な学習が始まります。
小学校では、教科の中で考え方を育てる学び方が中心です。
家庭でも学習を取り入れるべき理由

学校だけでは学びの差が広がりやすいのが現実です。 家庭で学ぶことで、子どもは自分のペースで力をのばすことができます。論理的に考える力が深まり、地域や学校ごとの違いを補うことができ、将来の大きな自信にもつながります。親としてその成長を支えることは、子どもの未来を守る大切な姿勢です。
論理的に考える力をさらに育てられる
学校では教科の中でプログラミング的思考を学びますが、それだけでは浅い理解にとどまることがあります。
家庭で繰り返し学ぶことで記憶が定着し、苦手を克服できます。中学や高校では小学校での理解を前提に授業が進むため、今のうちに家庭で学習を重ねることが大切です。
- 中学や高校の授業は小学校での理解を前提に進みます。
- 反復学習で記憶を定着させ、苦手を克服します。
- 家庭での学びが理解を深める大きな支えとなります。
- 学校では教科に組み込まれ、学びが浅くなる場合があります。
家庭での学びが、子どもの考える力を確実に育てる基盤になります。
地域や学校ごとの差を補うことができる
プログラミング教育は地域や学校ごとに差が大きく、半数近くの子どもが授業を受けていない実感を持っています。
調査でも50.6%が「やっていない」と回答しています。こうした格差を埋めるためには、家庭での学習が欠かせません。家庭で学ぶことで理解が深まり、未来の力につながります。
- 地域や学校で取り組みの差が出ています。
- 家庭で学ぶと理解を補うことが可能です。
- 50.6%の子どもが「授業なし」と回答した調査結果があります。
- 格差を埋めるには家庭での取り組みが重要です。
地域差を超えるために、家庭学習が子どもの未来を支える力になります。
家庭でできるプログラミング学習の方法
家庭でも工夫すれば楽しく学ぶことができます。 本や学習アプリを使ったり、遊び感覚で学べるおもちゃを取り入れたりすることが可能です。
また、動画やオンライン講座で学習を広げることもできます。イベントや体験会に参加して刺激を受け、さらに専門の教室に通うことで本格的に力をつけることもできます。
本を読んで基礎を学ぶ
書籍で学ぶ方法は、自分のペースで取り組めるうえに、パソコンがなくても始められるのが大きな強みです。絵本や教材を通して物語を楽しみながら自然にプログラミング的思考を身につけられるため、学習へのハードルが低く、初めての子どもにも取り入れやすい方法です。
- 難しい内容より、絵本から始めると学びやすいです。
- パソコンを使わずに取り組めるのが特長です。
- 世界で翻訳され、学校教材としても使われる本があります。
- 自分のペースでコツコツ学ぶのに向いています。
- 読書が好きな子どもにとって楽しく続けやすい方法です。
書籍は、楽しみながら考える力を伸ばす学習方法です。
学習アプリや教材を使う
プログラミング学習アプリや教材は、初心者でもゲーム感覚で直感的に学べるのが特長です。無料で使えるものも多く、実際にゲームを作る体験ができます。
ただし、端末やネット環境が必要で、長時間の利用は体への負担もあるため、時間を区切って使うことが大切です。
- 実際にゲームを作る体験ができます。
- デバイスやインターネット環境が必要です。
- 無料で使える教材が数多く用意されています。
- ゲーム感覚で楽しく学べるのが魅力です。
- 長時間の操作は体への負担になることがあります。
アプリや教材は、楽しく学びながら創造力を形にできる学習方法です。
おもちゃを通して遊びながら学ぶ
プログラミング玩具は、遊びを通して考える力を自然に育てられる方法です。親子で楽しめるため、勉強が苦手でも取り組みやすく、興味を持つきっかけになります。
年齢が上がると飽きやすいですが、好きになれば本格的な学習へつなげやすい点も魅力です。
- 遊びを通して考え方を学べます。
- 年齢が上がると飽きやすい面があります。
- 親子で一緒に楽しみながら学習できます。
- 興味を持つことで本格的な学習につなげやすいです。
- 勉強が苦手でも始めやすい方法です。
玩具を使った学びは、楽しく続けながら興味を学習へ広げる第一歩になります。
動画やオンライン講座を活用する
インターネット講座や動画コンテンツは、自由に学びたいことを選べて、実践的な内容にも取り組みやすい学習方法です。
プロが教える動画も多く、ひとりでも進めやすいのが魅力です。ただし、知りたい内容を探すのに手間がかかり、体系的に学びにくい点には注意が必要です。
- プロが行う講座で実践的に学べることがあります。
- 目的に合った動画を探す手間がかかります。
- 自分の興味に合わせて自由に学習できるのが特長です。
- 情報が整理されていないため体系的に学びにくい面があります。
- ひとりでも進めやすい学習方法です。
ネット講座や動画は、自由度が高く実践力を磨ける学習手段です。
イベントや体験会に参加する
プログラミングイベントやセミナーは、実際に体験しながら学べるため、興味や関心を高めやすい方法です。
その場で教えてもらえるので「できた」という体験が家庭学習につながります。ただし、日程調整や予約が必要で、内容が難しいと苦手意識を持つ可能性もある点には注意が必要です。
- 家庭学習につながりやすい体験ができます。
- 日程や予約など参加条件の調整が必要です。
- その場で教えてもらえるため理解が深まります。
- 子どものレベルに合わないと苦手意識を持つ可能性があります。
- 実際に体験することで興味や関心が高まりやすいです。
イベントやセミナーは、体験を通じて学ぶ意欲を引き出す大切な機会になります。
専門の教室に通う
プログラミング教室は、講師のサポートを受けながら体系的に学べるのが特長です。オンラインや家庭教師タイプもあり、子どもの予定に合わせやすい環境も整っています。
通学が必要な場合は時間の制約がありますが、挫折しやすい子でも「できた」という体験を積み重ね、学ぶ習慣をつくりやすい学習方法です。
- オンラインや家庭教師の形で学ぶこともできます。
- カリキュラムに沿って体系的に学習できます。
- 通学が必要な場合は時間の制約があります。
- 講師のサポートで初心者から上級者まで対応できます。
- 教室に通うことで学習習慣を身につけやすいです。
教室は、専門的な支えを受けながら継続して学べる安心の方法です。
Auto Amazon Links: プロダクトが見つかりません。
まとめ:小学生のプログラミング授業は必修?時期と内容は?教育の目的と家庭で取り入れるべき理由
結論から言えば、プログラミングの授業は子どもの未来にとって欠かせない学びです。すでに2020年から必修化され、算数や理科、音楽などの教科の中に取り入れられています。新しい科目ができたわけではなく、物事を筋道立てて考える力を育てるために組み込まれているのです。目的は難しい言語を覚えることではなく、問題を解決するために試行錯誤し、より良い答えにたどり着く力を養うことにあります。
しかし、教育の現場には地域や学校ごとに大きな差があります。調査でも半分近い子どもが授業を受けた実感がないと答えており、この差を放置すれば将来の力の差へと広がりかねません。だからこそ、家庭で学びを取り入れることが重要です。本や絵本を通じて楽しみながら考える力を磨くこともできますし、学習アプリや動画教材でゲームを作る体験をすれば、子どもは自然に論理的思考を積み重ねていけます。玩具で遊ぶ中でも仕組みを理解しやすく、興味が育てば本格的な学習へとつながっていきます。さらに、イベントや教室に参加すれば、自分が作ったプログラムで動かす体験を通じて、自信と学習意欲が深まります。
私は自分の子どもがプログラミングを学んだことで、勉強に対する取り組みが大きく変わったのを感じています。論理的に考える力はすべての学びに通じ、未来を切り開く基盤になります。教育の遅れが叫ばれる日本でこそ、家庭の力でその差を埋め、子どもが自信を持って世界に挑めるように支えていく必要があります。プログラミングを学ぶことは、ただの技術習得ではなく、これからの社会を生き抜く力を育てる大切な一歩です。


当サイトでは、小学生へプログラミングを学習させたいと考えている親御さん向けに、役立つ情報を中立的な立場から提供しています。プログラミング学習の重要性、そのメリットとデメリット、子どもたちが直面する可能性のある課題、そして学習を始めるための具体的な方法について、わかりやすく解説しています。当サイトの目標は、お子さんがプログラミングを通じて論理的思考を養い、創造的な問題解決能力を身につけ、将来様々な分野に進んでも活躍できるようサポートすることです。また、保護者様自身が子どもの学習をサポートするための知識を深めることもできます。